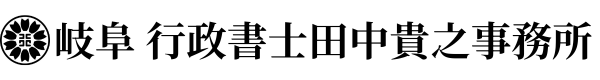【2025年版】生前贈与は相続対策の王道!メリットと注意点を徹底解説

相続税の負担を軽減し、家族間のトラブルを防ぐために、多くの方が実践している「生前贈与」。
生前贈与とは?
これにより、亡くなった後に発生する「相続税」の対象となる財産を事前に減らすことができます。 相続税の節税対策として非常に有効であり、資産のスムーズな承継にも役立ちます。
相続対策における「生前贈与」の役割
相続対策は大きく3つに分けられます。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 資産 | 相続時報酬対象額をメイン |
| 納税資金対策 | 相続税の支払いに備える、現金などで資金 |
| 資 | 相続人間のトラブルを防ぐために分けやすい資産を |
このうち、「資産圧縮対策」と「納税資金対策」に非常に効果的なものが生前贈与です。
年間110万円まで非現金!贈与税の基礎控除を活用
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは受贈者1人につき年間110万円までの贈与が非課税となる制度です。
【具体例】
子3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与すると… → 3,300万円の資産を非課税で移転!
さらに、孫や子の配偶者にも贈与をすれば、相続財産の圧縮効果はさらに大きくなります。孫への贈与は「一世代飛ばし」により、相続税の金額を1回軽減する効果も期待できます。
相続税軽減に有利な「直系尊属からの贈与」
直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子や孫へ贈与する場合、通常より低金利が適用されます。
注意!「定期贈与」見送らないために
贈与が成立するには、「贈与者と受贈者の契約」が必要です。 なお、以下のような場合には注意が必要です。
子名義の通帳に毎年同額を振り込む
贈与契約書を作っていない
通帳・印鑑を親が管理している
これらは「形式的な贈与」とみなされ、税務調査で否認される可能性があります。 さらに、毎年同額を贈与していると「定期贈与」と判定され、贈与税の非課税枠(110万円)が適用されないこともある。
対策としては以下の通り:
毎年、贈与契約書を作成する
贈与額・贈与時期を変える
受贈者が通帳・印鑑を管理する
生前贈与と相続税の加算制度に注意(2024年から7年に延長)
相続開始前の3年以内に受けた贈与は、相続財産として加算されます。 なお、2024年1月1日以降の贈与については、この加算対象期間が7年間に延長されました。
この加算対象には、孫や子の配偶者など、法定相続人以外も含まれる場合がありますので、慎重な計画が必要です。
生前贈与 × 生命保険で節税&納税資金対策
現金を生前に贈与し、それを生命保険に充てることで、より効果的な相続対策が可能になります。
【パターン①】親の死に備える場合
保険契約者:子
被保険者:親
保険金受取人:子
この場合、親からの贈与をうけた子が保険料として支払い、親の死亡時に子が保険金を受け取る仕組みです。 受け取った保険金は、相続税の納税資金として活用できます。
※注意:親が直接保険料を支払うと、相続税の対象になる恐れがあります。
【パターン②】子や孫の将来の資産形成に活用
保険契約者:子または孫
被保険者:子または孫
受取人:その相続人
贈られた現金を用いて、将来の教育資金や結婚資金など、人生設計に沿った資産形成が可能です。
まとめ|生前贈与は早めの計画がカギ!
生前贈与は、相続税の節税、贈与資金の確保、そして家族の円満な財産承継を実現するための強力な手段です。
生前贈与を考えるなら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
✅ 無料相談受付中!
「うちの場合はどうしたらいいですか?」「贈与契約書作成ってどうやるの?」など、生前贈与に関するお悩みはお気軽にご相談ください。