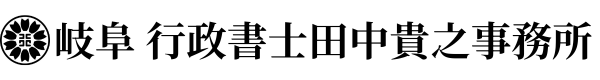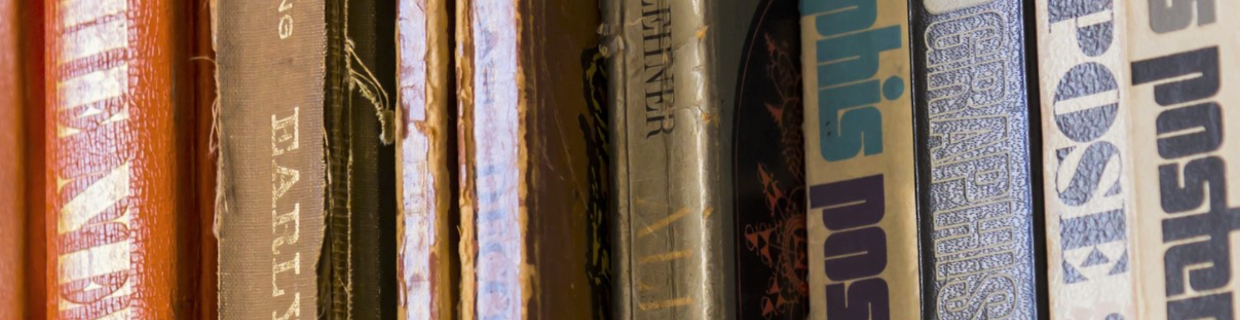遺産はこうして分けられる|遺産分割協議の流れと注意点をわかりやすく解説

相続が発生すると、まず「相続人の確定」と「遺産(相続財産)の把握」が行われ、その後に行われるのが遺産分割協議です。遺産分割の基本的な流れや注意点、相続人に未成年者や認知症の方、音信不通者がいる場合の対応などを解説します。
遺産分割協議とは?全員参加・全員決意が原則
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、遺産を誰がどのように相続するかについて話し合う手続きです。
被相続人が遺言を残している場合は、遺言書の内容が優先されますが、遺言がない場合はこの協議によって話し合う必要があります。
多数決では決まらない!協議は「全員の同意」が必要
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員の合意がなければ成立しません。
同様に、相続人が5人いて3人が賛成しても、反対する人が1人でもいれば協議は成立しません。このため
、協議が長期化するケースも少なくありません。
相続人が音信不通?家庭裁判所で「相続者財産管理人」や「失承宣告」の申立てを
音信不通の相続人がいる場合の対応
相続人の中に信音不通や所在不明の人がいると、協議を進めることができません。
「失追跡宣告」で死亡扱いにすることも可能
音信がなく所在が分からない人がいる場合に7年間生死が不明な場合は、家庭裁判所に失踪宣告(しっそうせんこく)を申し立てることができます。
失踪宣告とは、7年間以上生死不明者を死亡したもの」と認定し、これによりその人の相続も開始されます。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の対応
未成年者が相続人の場合は「特別代理人」が必要
相続人に未成年者がいる場合は、独自で法律行為ができないため、通常は親が代理人になります。
ただし、親も相続人となっている場合には利害が衝突するため、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらう必要があります。
例:夫が死亡し、相続人が妻と成人した子、未成年の子の場合、妻は未成年の子の代理人にはなれません。
認知症の相続人がいる場合は「成年後見制度」を活用
認知症などで判断能力がない方が相続する場合は、成人後見人、保佐人、補助人をつける必要があります。成人後見人が選ばれた
場合は、その人が代理で遺産分割協議に参加します。
保佐人・補助者がついた場合は、本人が参加しつつ、内容に同意を得る必要があります。
遺産分割協議書作成と、法定相続分の考え方
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成
遺産分割協議が成立したら、その内容を詳細に記した遺産分割協議書を作成します。これは法律で義務付けられたものではありませんが、預貯金の名義変更や不動産の登記手続きに必要となります。
協議書には、確定した日付、相続人全員の署名・実印の押印が必要です。
解決があれば自由な分け方も可能
相続分の割合(法定相続分)は民法で定められた「法定相続分」で決められますが、相続人の全員の合意があれば、どのような分け方でも可能です。
例えば、3人兄弟のうち1人がすべてを相続するという内容も、全員が同意すれば成立します。
非嫡出子の相続権と注意点
2013年の最高裁判で法定相続分が平等に
以前は、法律婚によらない子(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子の半分とされていましたが、2013年の最高裁判決でこの規定は違憲とされ、民法も修正されました。
現在では、嫡出子・非嫡出子とも相続分は同等です。
非嫡出子の相続には「認知」が必要
非嫡出子が相続権を得るには、父親からの認知が必要です。
認知は生前に限らず、父の死後でも可能であり、死亡から3年以内であれば裁判で認知請求することができます。
まとめ|複雑なケースは専門家への相談が安心
遺産分割協議は、一見すると単純な話し合いのように思えますが、実際にはさまざまな法律上の問題や手続きがあり、争族に発展してしまうこともあります。
相続でお悩みのことがあれば気軽にお問合せくださいませ。