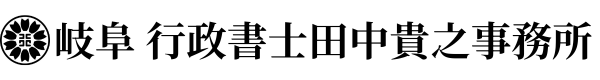【相続トラブルを防ぐには?】遺産分割協議が「争族」を決める理由とその対策

相続の話になると、「争族(そうぞく)」という言葉に注意する必要があります。
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、遺産分割協議の場面で思わぬトラブルになるケースは少なくありません。
今回は、なぜ遺産分割が争族の引き金になるのか、そしてその対策としてできることについて、わかりやすく解説します。
なぜ「遺産分割協議」がもめごとの原因になるの?
法律では「法定相続分」を尊重し、遺産を公正に選択することが基本とされています。
しかし現実には、相続人それぞれの気持ちや状況が絡み合い、「不公平だ!」と感じる場面が多いのです。
特に、遺産の多くが「不動産」の場合は要注意です。
現金のようにパッと分けられず、「どうしようか」で意見が食い違いやすくなります。
遺産の分け方は主に3つ
① 現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産をそのままの形で任意による方法です。
例えば、家は長男、口座は次男というように分けます。
👉不動産は、現物分割ではトラブルになりがちです。
②換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を賢く売って現金に変更し、そのお金を選択する方法です。
👉不動産を売却し、現金化します。
👉 **税金(譲渡所得税)**がかかる場合もありますので注意が必要です。
③代償分割(だいしょうぶんかつ)
例えば「長男が家を相続して、他の兄弟にお金を支払う」というように、遺産を受け取った人が他の相続人にお金(代償金)を支払うことで解決する方法です。
👉不動産が絡む場合、最もトラブルを避けやすい方法ですが…
👉問題は「代償金をどうやって準備するか」。
代償金の準備には「生命保険」を活用できる!
代償分割をスムーズに継続するために活用されるのが、「生命保険」です。
相続させたい親が、家を相続させたい子を生命保険金の受取人にしておく
その子が受け取った保険金を、他の兄弟に代償金として支払う
そうすれば、不動産も守られますし、他の相続人も納得しやすくなります。
ただし注意点も!
生命保険金は遺産分割の対象外ですが、まれに相続税の対象になることがあります
受取人の指定を間違えると、実際に争族になることもあります
「特別受益」と「寄与分」でもめることも…
相続でよく話題になるのが、「特別受益」と「寄与分」です。
この2つが原因で、感情的なもつれに発展するケースもあります。
特別受益とは?
生前に、ある相続人だけが親から特別な援助を受けていた場合、それを踏まえて遺産を相続する制度です。
たとえばこんな:
長男だけが家を買うときに1,000万円援助してもらった
一人だけ留学費用を出してもらった
結婚の時に高額な持参金を受け取った
これらは「特別受益」として扱われ、他の相続人のバランスをとるために差し引かれます。
✅配偶者居住制度:配偶者に贈られた自宅は、原則として持ち戻さなくてよいとされています(婚姻期間20年以上の場合)
寄与とは?
親の介護や事業の手伝いなどで、特別に貢献した人が遺産を受け取れる制度です。
「長女が10年間介護したのに、他の兄弟と同じ相続分…?」という不公平を調整するための仕組みです。
また、相続人でなくても貢献があれば「特別料」としてお金を請求できるようになっています。
【まとめ】争族を防ぐために、今できる準備を!
相続は「財産の分け方」だけでなく、家族の気持ちや感情が大きく関わる問題です。
ですから、事前の準備がとても大切です。
✔ 争族を防ぐためのポイント
不動産は「代償分割」や「生命保険」でトラブル防止を
「特別受益」や「寄与分」について早めに整理しておく
できれば遺言書を作成しておく
不安な点は、行政書士など専門家に相談する
家族の絆を守るためにも、「相続の話は元気なうちに」始めてみませんか?