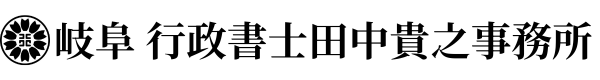農地転用における三条許可制とは?|手続きの流れや注意点を行政書士が解説

「農地を駐車場や建物用地に転用したいけれど、三条許可制ってなに?」
「市街化調整区域の農地でも転用できるの?」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、この記事では「三条許可制」の基本から、対象となる土地、手続きの流れ、よくある誤解とその対処法までわかりやすく解説します。
農地転用を成功させるためのポイントも解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
三条許可制とは?|農地転用の法的基礎を知る
農地法の第3条・第4条・第5条とは
農地転用は農地法によって厳しく制限されており、以下のような条文に基づいて許可制が設けられています:
- 第3条:農地のまま売買・貸借する場合
- 第4条:所有者が農地を自ら宅地などへ転用する場合
- 第5条:第三者に農地を譲渡し、転用する場合
このうち「第4条・第5条」の転用申請に対して厳格な審査が行われる仕組みが「三条許可制」と呼ばれています。
なぜ三条許可制があるのか?
農地は日本の食料供給の基盤であり、むやみに減らしてしまうと将来的な農業維持に支障が出ます。そのため、国は農地の転用について特に慎重に審査する仕組みを設けています。
三条許可制が必要なケースとは?
農振農用地区域の農地
市町村が策定する「農業振興地域整備計画」により指定された農地は、原則として農業以外の用途に転用できません。
まずは「農振除外」の手続きを行わなければ、三条許可の審査対象にもなりません。
市街化調整区域内の農地
市街化調整区域では、都市計画により宅地化が制限されています。
この区域での農地転用には、農地法の許可だけでなく、都市計画法や建築基準法に基づく許認可も必要です。
開発目的を伴う農地利用
宅地開発や資材置場、駐車場など営利目的での利用を行う場合には、転用の正当性や公共性が求められます。
計画が曖昧なままでは許可されない可能性が高いです。
三条許可制における農地転用の流れ
1. 農業委員会への事前相談
まずは市町村の農業委員会へ相談し、該当地が転用可能かを確認します。
多くの場合、現地調査・図面確認・計画説明が必要です。
2. 必要書類の準備
- 農地転用許可申請書
- 土地登記事項証明書
- 位置図・平面図・写真
- 利用計画書・建築計画書
3. 農業委員会→知事(または代理市町村)への審査・許可
申請内容に基づき、農業委員会と都道府県(または委任された市町村)が審査を行います。
審査期間は1~3か月が一般的ですが、農振除外が絡むと半年以上かかることもあります。
4. 許可後に転用・地目変更
許可取得後に工事を開始し、完了後に「地目変更登記」を行います。
許可前の着工は違法転用となるので絶対に避けましょう。
三条許可制でよくある誤解と注意点
「宅地にすればすぐ建てられる」は誤解
農地を宅地にするには、法的な許可と都市計画の整合性が不可欠です。
「耕作していない農地は自由に使える」は誤解
登記上「農地」となっている限り、現況が耕作放棄地でも転用には許可が必要です。
「市街地に近いから大丈夫」は通用しない
調整区域は市街化を抑制するエリアであり、周辺の利便性に関係なく原則として転用不可です。
三条許可制の農地転用は行政書士に相談を
三条許可制の申請は、法的知識・地域事情・都市計画との整合性が複雑に絡むため、自己判断で進めると高確率で不許可となります。
行政書士に依頼することで:
- 対象農地の調査と判断
- 農業委員会との折衝
- 書類作成と補正対応
- 必要に応じた他法令(開発・建築)との連携
など、申請を確実に前進させることができます。
まとめ|三条許可制の理解が農地転用成功の鍵
- 「三条許可制」とは、農地転用の中でも特に慎重な審査対象となる制度
- 農振地域や市街化調整区域では、事前相談と制度理解が不可欠
- 自己判断はリスクが大きいため、早めに専門家へ相談を
【初回無料相談受付中】岐阜県での農地転用はお任せください
当事務所では、岐阜県内の農地転用(三条許可制)に数多く対応してきた実績があります。
「この土地は転用できる?」「農振除外ってなに?」「市街化調整区域だけど大丈夫?」など、お気軽にご相談ください。
▶ 電話番号:090-4084-4259
▶ メール:tanaka@gyoseisyoshi.岐阜.jp
▶ ホームページ:https://gyoseisyoshi.岐阜.jp