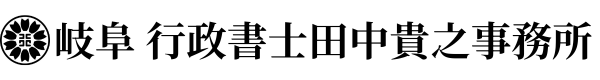農地転用で不許可になるのはなぜ?|よくある失敗事例と回避のポイント

「農地転用を申請したけど、許可が下りなかった…」
「これから申請予定だが、不許可になる可能性があるか不安…」
この記事では、実際にあった農地転用の不許可事例をもとに、どのようなケースで却下されるのかを解説します。さらに、不許可を防ぐためのポイントや、専門家に依頼すべき判断基準についてもご紹介します。
農地転用とは?許可が必要な理由
農地転用とは、農地を住宅・倉庫・駐車場などの農業以外の用途に変更することです。農地は「農地法」によって厳しく保護されており、無断で転用すると罰則の対象となります。
農地転用を行うには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要で、申請には一定の要件を満たす必要があります。
不許可になる主な事例とその理由
1. 利用目的が曖昧で、計画が不明確
例:「家庭菜園用の建物を建てる」「趣味の作業場として使う」など、明確な事業計画や必要性が乏しいと判断され、不許可となるケースがあります。
2. 市街化調整区域での申請
市街化調整区域では、原則として農地転用は認められていません。例外はありますが、都市計画に適合しない限り、許可は極めて難しい地域です。
3. 農業委員会への事前相談をしていない
申請書だけを提出しても、事前相談がなければ「趣旨や必要性が理解されていない」と判断されることがあります。特に計画内容に疑義があると不利になります。
4. 現況と登記内容が一致していない
登記簿上は農地だが、実際には荒れ地や山林とみなされている場合、手続きの中で申請内容と現況の矛盾が指摘されることがあります。
5. 周辺住民や水利組合の同意が得られていない
農地の転用には、周辺環境への配慮が重要です。水路の使用や騒音、景観問題などでトラブルが起こる可能性がある場合、反対の声が不許可の一因となることがあります。
実際の不許可事例から学ぶ|よくある失敗パターン
事例1:市街化調整区域で住宅建設を申請 → 不許可
転用先が市街化調整区域で、都市計画上の整合性が取れなかった。事前相談を行っておらず、建築物の用途に公共性がなく却下。
事例2:作業小屋としての転用 → 計画内容が不十分で不許可
具体的な設計図や利用計画を示さず、「将来的に使うかも」といった曖昧な理由で却下。
事例3:水利組合からの同意が得られず → 不許可
転用予定地に隣接する水路の使用権について明確な合意が得られず、地域との協調性に問題があると判断された。
不許可を避けるためのチェックポイント
- 転用目的・建物用途を明確にする
- 農業委員会・市町村と事前に相談する
- 登記情報と現況を確認・一致させる
- 周辺住民や関係者との合意形成を図る
- 調整区域であれば都市計画との整合性を確認
不許可になってしまったら?再申請のポイント
農地転用が不許可になった場合でも、原因を明確にし、再申請することは可能です。ただし、最初の申請内容と同様のまま再提出しても再度却下される可能性が高いため、以下の対応が重要です。
- 農業委員会との面談・フィードバックの確認
- 転用計画の見直し・再構成
- 必要に応じて専門家(行政書士など)に依頼
農地転用に不安があるなら専門家へ相談を
農地転用は法律や地域ごとの事情に大きく左右されるため、自己判断はリスクが高いのが現実です。
行政書士などの専門家に依頼すれば、必要書類の作成や行政との折衝も代行可能です。
不許可のリスクを最小限に抑え、スムーズな申請を行うためにも、早めの相談をおすすめします。
【初回無料相談受付中】岐阜県での農地転用はお任せください
当事務所では、岐阜県内を中心に農地転用の手続きサポートを行っております。
「自分の農地が転用できるか不安」「過去に不許可になったが、再挑戦したい」など、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
▶ 電話番号:090-4084-4259
▶ メール:tanaka@gyoseisyoshi.岐阜.jp
▶ ホームページ:https://gyoseisyoshi.岐阜.jp