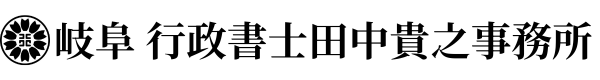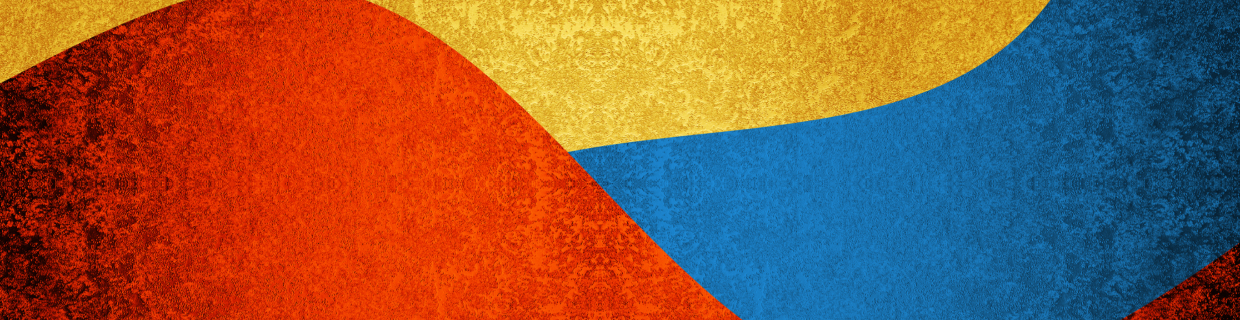農地に建物を建てるには?「開発許可」と「農地転用許可」の違いと正しい手続き順を徹底解説【2025年版】

「農地に家を建てたいけど、どんな許可が必要?」「開発許可と農地転用ってどう違うの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「開発許可」と「農地転用許可」の違い、手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。
特に市街化調整区域や農地を活用したい方にとっては、正しい知識と申請の順番を知ることが成功のカギです。トラブルを避けてスムーズに土地活用を進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
農地に建物を建てるには、どんな許可が必要?
結論から言うと、農地に建物を建てるには「農地転用許可」と「開発許可」の両方が必要になるケースが多いです。
農地転用は「農地法」に基づく許可で、農地を宅地や資材置き場など農業以外の用途に使う際に必要です。一方、開発許可は「都市計画法」に基づくもので、土地に建物を建てるために宅地造成などを行う場合に必要となります。
たとえば、自宅を建てるだけのつもりでも、その土地が農地であり、市街化調整区域内であれば、次のような2つの許可が必要です。
- 農地転用許可:農地を非農業用途(宅地)に変える
- 開発許可:建物を建てるための土地造成・都市計画上の整合確認
これらは別個の法律・管轄のもとで審査されるため、いずれか一方だけでは不十分です。無許可で造成・建築を行うと、原状回復命令や罰則の対象となることもあるため、必ず事前に確認を行いましょう。
開発許可と農地転用、どちらを先に申請すべき?
原則は「開発許可」→「農地転用許可」の順番で申請するのが正しいとされています。
なぜなら、農地転用の許可審査では「その土地が本当に建物に使えるのか?」が問われます。つまり、開発許可が下りていない状態では、そもそもその土地に建物を建てる正当性が証明できず、農地転用許可も下りにくくなります。
一方で、自治体によっては例外的に「同時申請」や「農地転用先行」が可能なケースもあるため、事前に役所への相談が必須です。
▼具体例
- 岐阜県A市:開発許可が下りてからでないと農地転用が受理されない
- 岐阜県B町:事前協議後に同時申請可能、担当課が連携審査
このように、同じ県内でも自治体によって対応が異なることがあるため、自己判断で進めずに、必ず「事前相談」+「行政書士等の専門家の助言」を活用しましょう。
市街化調整区域内の農地でも建物は建てられる?
市街化調整区域では原則として開発行為が制限されていますが、例外的に建物を建てられるケースもあります。
たとえば以下のような場合です。
- 自己の居住を目的とした住宅建築(開発許可基準に適合する必要あり)
- 既存の集落内での建替えや同一敷地内での用途変更
- 市の「立地適正化計画」や「条例指定区域」内で認められる場合
ただし、これらも行政との協議のうえ、開発許可と農地転用許可を得なければ実現できません。市街化調整区域内は、都市の無秩序な拡大を防ぐために厳しい制限が設けられており、「例外」として認められるかどうかが最大のポイントになります。
専門家の調査によって「許可の可能性があるかどうか」が見えてくるため、土地を取得する前の段階での確認が理想的です。
行政書士に依頼するメリットとは?
これらの許可手続きは、法令だけでなく地域ごとの行政運用にも大きく左右されます。行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 複雑な書類作成・手続きをすべて代行してもらえる
- 事前相談から立地調査・協議の立会いまで一貫対応
- 自治体ごとの審査傾向や実例に基づく申請が可能
農地転用と開発許可は、役所によって求められる書類や審査期間も異なり、一般の方が独力で進めるのは困難です。早く・確実に許可を得るためには、経験豊富な行政書士のサポートが強い味方になります。
まとめ|開発許可と農地転用は慎重に、順序と地域のルールを確認しよう
農地を建築や事業利用に転用するには、「農地転用許可」と「開発許可」という2つの異なる手続きが必要です。特に市街化調整区域においては、両方の許可が取れない限り、一切の開発行為が認められません。
許可を得るためには、自治体の運用を事前に確認し、正しい順序と書類で進めることが不可欠です。少しでも不安がある方は、まずは行政書士などの専門家に相談してみましょう。
岐阜県での農地転用・開発許可は当事務所にご相談ください
当事務所「岐阜 行政書士田中貴之事務所」では、農地転用や開発許可に関するご相談を多数取り扱っています。
- 初回相談無料
- オンライン・訪問相談対応
- 農地調査から事前協議・申請代行までワンストップでサポート
土地の活用でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。