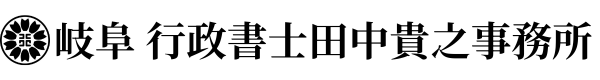贈与税の特例制度を活用して節税対策!制度別に詳しく解説

贈与税には、さまざまな特例制度が設けられており、これらを上手に活用することで贈与税を負担せずに財産を移転できます。ただし、複数の相続人がいる場合は、特定の相続人への偏った贈与が他の相続人の不公平感を招く可能性があるため、バランスよく行うことが重要です。
①配偶者控除:婚姻20年以上の配偶者に自宅を贈与
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅または自宅購入資金を贈与する場合、基礎控除(110万円)に加え2,000万円までが非課税となります。
さらに、2019年7月1日の民法改正以降、この贈与は特別受益に該当せず、相続財産に加算されないため、安心して利用することができます。
②住宅取得等資金の贈与:子や孫への住宅購入資金援助
2024年1月1日~2026年12月31日の期間において、両親や祖父母などの直系尊属が18歳以上の子や孫に自宅の購入または増改築資金を贈与する場合、基礎控除(110万円)に加えて特別な非課税枠があります。
省エネ住宅など一定条件の住宅には、住宅性能証明書などの書類を贈与税申告書に添付する必要があります。
③教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与:将来の資金援助
両親や祖父母などの直系尊属が、子や孫名義で金融機関に資金を一括贈与すると、一定額まで贈与税が非課税となります。
非課税となる資金には以下の2つの用途があります。
- 教育資金
- 結婚・子育て資金
これらの資金は、それぞれ用途により受贈者の要件や非課税限度額が異なります。資金は指定された用途にのみ使われ、金融機関が領収書の確認・保管を行います。
なお、この特例制度は贈与を受ける前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は利用できません。また教育資金については、受贈者が23歳以降に支払う学校等以外の費用(一部の教育訓練を除く)は対象外となります。
贈与特例制度を活用する際のポイント
贈与税の特例制度を活用することで、財産を効率的かつ負担少なく移転できます。ただし、不公平感が生じないよう、相続人間での配慮が必要です。
特例制度の具体的な活用方法や詳細についてご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。