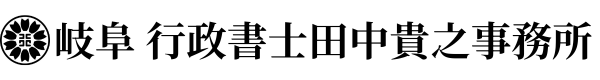相続税の課税対象者が増加中!二次相続のトラブルを防ぐ方法

近年、相続税を支払う方が増加しています。その理由は、2015年以降、相続税の基礎控除額が引き下げられたためです。本記事では、相続税の最新の動向と、特に注意が必要な「二次相続」の対策について解説します。
相続税の課税対象者が増えた背景
2015年に基礎控除額が大幅に引き下げられ、それ以前は課税割合が4%台だったのが、改正後は約8%に急増しました。2021年には全国で9.3%となり、特に東京都(18.1%)、愛知県(14.9%)、神奈川県(14.1%)など都市部での課税割合が高くなっています。
相続税が他人事ではなくなった現在、ご自身やご家族が将来相続税を負担する可能性が高まっています。
二次相続が一次相続よりもトラブルになりやすい理由
一般家庭では相続が二度起こります。最初の相続を「一次相続」と呼び、夫婦の一方が亡くなった際に配偶者や子どもが相続します。その後、配偶者が亡くなったときに子どもたちだけで相続するのを「二次相続」と呼びます。
一次相続よりも二次相続の方がトラブルが多いといわれます。その理由として、一次相続では子どもたちが残された配偶者を気遣い、遠慮する傾向にありますが、二次相続では兄弟間での経済的な主張が表面化し、トラブルが深刻化しやすくなります。また、二次相続では相続税の軽減措置が利用しにくく、税負担が大きくなりがちです。
トラブルを防ぐためにできること
相続争いは家族全体を不幸にします。トラブルを防ぐには、生前から相続の基礎知識を身につけ、適切な対策をしておくことが重要です。
- 事前に遺言書を作成しておく
- 財産分割の方法を生前に話し合う
- 税負担を考慮した資産運用や生前贈与を活用する
まとめ
相続税の対象者は年々増えており、特に二次相続はトラブルになりやすいため、早めの対策が必要です。事前準備を徹底し、ご家族が円満に相続できるよう備えておきましょう。
相続についてさらに詳しく知りたい方や具体的なご相談を希望される方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。