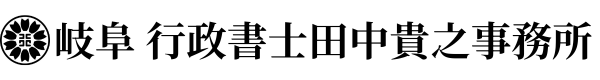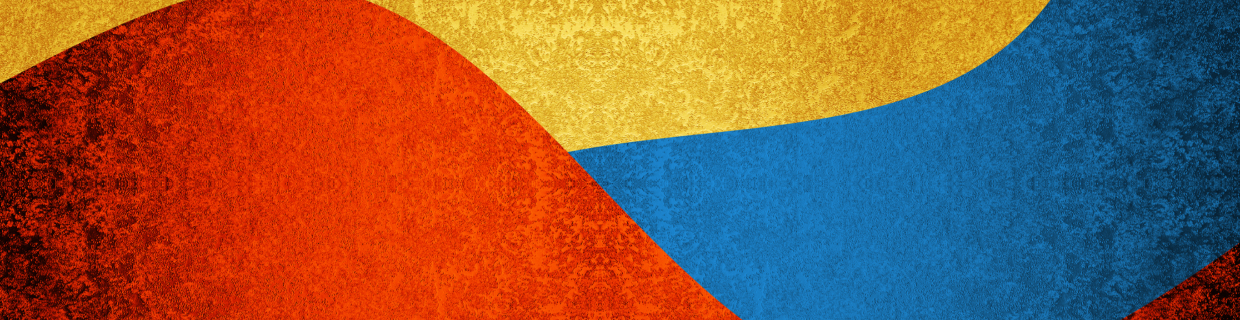公正証書遺言の作成|失敗しない作成手順と注意点を行政書士が解説

「どんな内容を入れていいのか?」「公正証書遺言の書き方が分からない」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、公正証書遺言の基本から作成手順・必要書類・注意点までわかりやすく解説します。
相続トラブルを防ぎ、大切な方へ想いを正しく残すための参考にしてください。
✅公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が作成し、公文書として有効性を持つ遺言のことです。
他の遺言方式(自筆証書・秘密証書)と比較しても、法的な有効性・安全性が最も高いとされています。
メリットは以下のとおり:
書式不備による無効リスクがない
家庭裁判所での検認手続きは不要です
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない
📝公正証書遺言の正しい書き方と作成手順
1. 内容を事前に整理する
以下を明確にしましょう。
誰に財産を残すか(相続人・第三者など)
何を遺すか(不動産・預金・株式・車など)
特別な希望(介護してくれた子にたくさん相続させたい等)
👉箇条書きでも良いので、メモを作成しておくと、後の打ち合わせがスムーズです。
2.必要書類を準備する
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 代理人本人 | 本人確認書類(運転免許証) 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) |
公的書類 |
| 相続人・被相続人 | 戸籍謄本・住民票など | 身分証明 |
| 財産関連 | 登記事項証明 | 財産の特定の必要 |
3. 公証人役場へ予約・事前打ち合わせ
公証人役場に連絡して予約
作成内容の草案や資料を提出
公証人が内容を確認・文案を作成
👉行政書士が入って、文案整理や連絡もスムーズに行きます。
4. 証人を2名同伴する
公正証書遺言には、証人が2名必要です。
以下のような方は証人になれません。
未成年者
推定相続人や受遺者、およびその配偶者・直系血族
公証人の事務所職員
※証人がいない場合は、公証人役場に依頼することも可能です(有料)。
5. 作成・署名・保管
公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者・証人が内容を確認後、手動・押印します。
完成した遺言書は以下のように保管されます。
【原本】公証人役場で厳重保管
【正本・謄本】遺言者へ渡す(ご家族や行政書士が保管)
💰公正証書遺言の費用はいくらかかりますか?
費用は「財産の総額」によって異なります。任意は以下のとおりです。
| 遺産 | 公正証書遺言の手数料 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 約5〜7万円程度 |
| 1億円未満 | 約8〜10万円程度 |
※これに加えて、証人費用・専門家報酬(行政書士など)がかかることもあります。
⚠公正証書遺言を書く際の注意点
● 遺留分に注意
相続人には「遺留分」という最低限の取り分があり、それを侵害するとトラブルのもとになります。
➡例、全財産を特定の子どもに遺すような内容には注意してください。
● 認知症のリスク
公正証書遺言は意思能力(判断能力)があるうちに作成します。
➡ 高齢者の場合は早めの作成がおすすめです。必要に応じて、医師の診断書を準備しましょう。
●書き込みに不安がある場合は専門家へ
形式は公証人が整えてくれますが、内容整理や財産評価・遺品整理などは専門的な知識が必要です。
➡ 不安な方は行政書士などの専門家にご相談しましょう。
📌公正証書遺言の執筆まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書 | 口述→公証人が書く、証人 |
| 必要書類 | 本人確認書類、戸籍謄本 |
| 料金目安 | 5〜10万円(その他に証人・専門家費用必要) |
| 注意点 | 遺留分配慮・判断能力・早期準備が必要 |
👨⚖️公正証書遺言で後悔しないために
相続は「争族」となるリスクを常に持っています。
しっかりとした準備が、家族への最大限の配慮です。
✅公正証書遺言の内容整理
✅書類準備・証人手配
✅相続トラブル防止のアドバイス
ご不安な点があれば、行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。