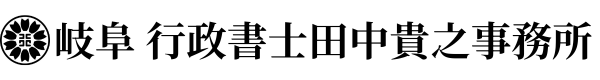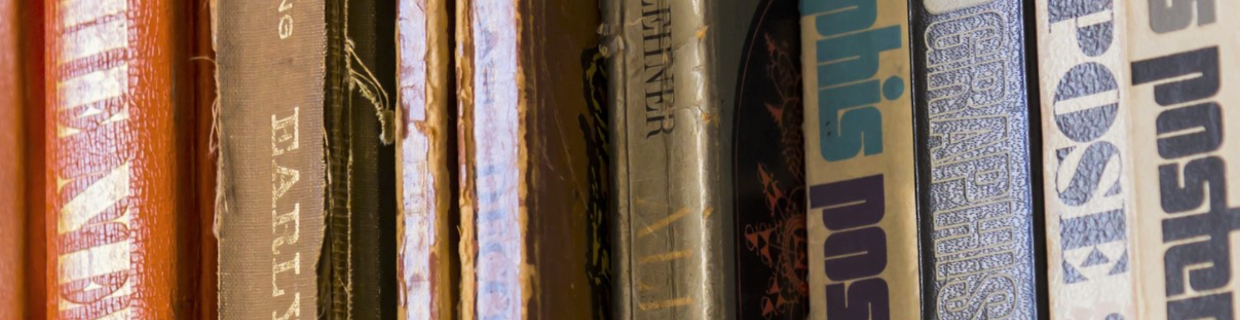【行政書士監修】遺言書が無効になるケースとは?よくある失敗と対策を解説
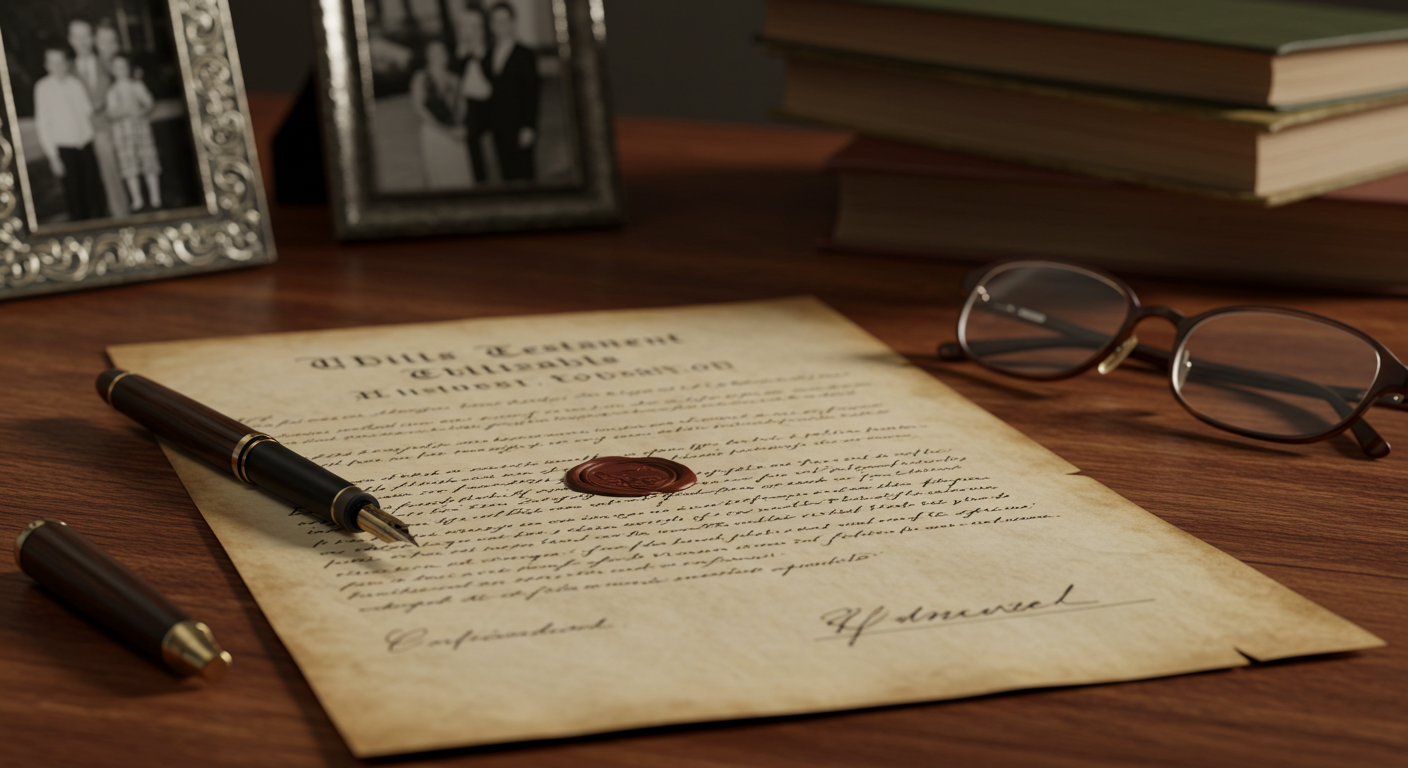
「遺言書を見つけたけど、これって本当に有効なの?」
「自分で書いた遺言書、法的に大丈夫かな…?」
相続トラブルを防ぐために作ったはずの遺言書が、形式不備や記載ミスによって“無効”になることがあります。
この記事では、遺言書が無効と判断される代表的なケースや注意点、有効な遺言書にするためのポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。
遺言書が無効になる主なケース
① 遺言者に「遺言能力」がなかった
遺言書は15歳以上かつ意思能力がある人でなければ作成できません。
認知症や精神障害で判断力が著しく低下していた場合、作成時に有効な判断能力がなかったとみなされ、遺言は無効になることがあります。
② 自筆証書遺言に必要な要件が欠けている
自筆証書遺言は、全文を自書し、日付・氏名・押印がなければ無効です。
パソコンや代筆、ハンコの押し忘れ、日付が不明確(例:「令和〇年〇月吉日」)な場合も注意が必要です。
③ 公正証書遺言で証人が不適格だった
公正証書遺言には証人が2人必要ですが、以下の人は証人になれません:
- 未成年者
- 推定相続人やその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族など
これらに該当する場合は、手続きが無効になります。
④ 本人の意思によらずに作成された遺言
誰かに脅されて書かされたり、勝手に書かれた(偽造・代筆)遺言書は当然無効です。
証拠が残っていれば、遺言無効確認訴訟の対象になります。
⑤ 遺言内容が曖昧・矛盾している
「長男に家をやる」と書いても、不動産の所在地や地番が明確でなければ執行できません。
また、2つの遺言書に異なる内容が書かれている場合、どちらが有効かで争いになることもあります。
⑥ 日付の記載が曖昧・特定できない
複数の遺言書がある場合、最新の日付の遺言が有効とされます。
「〇月吉日」などの曖昧な記載では、有効性が否定される可能性があります。
遺言書が無効になるとどうなる?
遺言書が無効になると、民法の法定相続分に従って相続されることになります。
その結果、遺産を特定の人に残すつもりだった意志が反映されず、「争族(そうぞく)」が発生するリスクも高まります。
有効な遺言書にするための3つのポイント
① 正しい形式で作成する
自筆証書遺言・公正証書遺言にはそれぞれ法定のルールがあります。
自信がなければ、法務局の遺言保管制度の活用も検討しましょう。
② 書き方に注意し、財産の特定を明確にする
財産の住所・地番・口座番号など、特定できる情報を明記することで、無効やトラブルを防げます。
③ 専門家に内容を確認してもらう
行政書士や弁護士などの専門家に相談することで、形式的ミスや法的不備を事前に防げます。
特に高齢者の方は、医師の診断書などで意思能力を証明しておくと安心です。
こんなときは行政書士へご相談ください
- 高齢の親が遺言を書いたが、内容が不安
- すでに複数の遺言が見つかり、どれが有効か分からない
- 自分で遺言書を書きたいが、正しい方法を知りたい
- トラブルを避けるために公正証書で作成したい
まとめ|「有効な遺言書」が残す家族への最大の思いやり
せっかく遺言書を作っても、無効では意味がありません。
有効な遺言書を残すことで、家族の安心・相続トラブルの回避につながります。
少しでも不安がある場合は、専門家へのご相談をおすすめします。
岐阜での遺言書作成なら|行政書士田中貴之事務所へ
当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートを行っております。
岐阜エリアでの相続・遺言相談に強く、初回相談は無料です。
📍 住所:岐阜県瑞穂市穂積928-1
📞 電話:090-4084-4259
🌐 ホームページ:https://gyoseisyoshi.岐阜.jp
📧 メール:tanaka@gyoseisyoshi.岐阜.jp